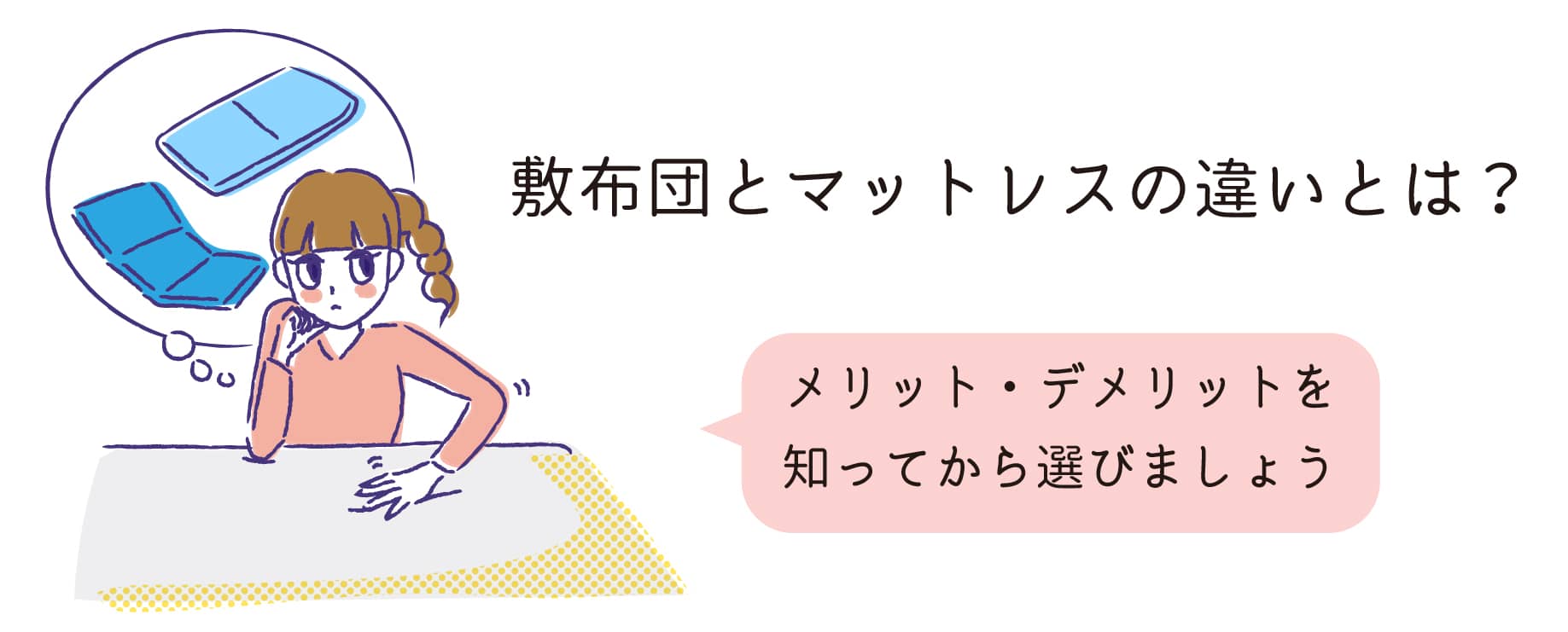
 リンコ
リンコこんにちは!「ぐっすりねむり隊」のリンコです。
敷き寝具を選ぶ際、まずは敷布団? マットレス? 一体どちらを購入すれば良いのか悩んでいませんか?
より良い睡眠を追求するためには、身体をしっかり支える寝具を選ぶのが大切です。
そこで今回は、ベッド用のマットレス以外の「機能性マットレス」と「敷布団」との違いや選び方について、櫻道ふとん店の『ふとんマイスター』にお聞きしてきました!
敷布団、マットレスの違いをきちんと知り、それぞれの環境に合った寝具でぐっすり眠れる環境をつくりましょう。
敷布団とマットレスの違いとは?メリット・デメリットを知ってから選びましょう
1.マットレスと敷布団の違いとは?
寝具選びを始める前に、敷布団とマットレスの違いについて詳しくご紹介していきましょう。どちらも同じように体の下に敷く寝具ですが、構造が違えば使い方や体に与える影響、寝心地まで違います。3つの視点から違いを解説するので、自分の使い方に合ったものを見つけましょう。
まず、敷布団とマットレスの違いは、
1.厚みの表示があるかないか
2.身長に対するサイズ(長さ)の計算方法
3.西洋生まれか日本生まれか
の3つです。
まずは、これら3つの違いについて解説します。
1-1.敷布団には厚さの表示がない
○敷布団の表示には、横×縦の表示しかありません。(例)「105×210」など
○マットレスには、厚み×横×縦の3つの表示があります。(例)「18×95×195」など
敷布団とマットレスでは基本的に製造方法が違います。
敷布団は着物の生地を縫い合わせて綿を詰めます。着物の生地は各地方や織物の製法によって多少の違いはありますが、おおむね37cmから38cmの巾でできており、11.5mで一反となります。 この生地を横に3枚縫い合わせて製作するため、105cmの幅の敷布団ができあがります。
マットレスは、ソファーを作る時と同じ発想で作られます。
スプリング性のあるものを積み重ね、それを丸ごと布で包み込む方法です。ベッドメイキングの発想ですね。したがって敷布団とは違い、はじめから厚み×横×縦があるのです。
1-2.敷布団とマットレスの違いはサイズ
敷布団の長さは200cmや210cmが中心ですが、マットレスは195cmが主流です。
敷布団に適したサイズ(長さ)は、実は寝具技能士の国家検定試験にも出題されます。答えは、身長+35cmです。身長160cmの方の場合、自分に合った敷布団のサイズ(長さ)は160cm+35cm=195cmとなります。
マットレスの場合でも、フローリングや畳に直接使用する場合は、敷布団の計算方法が良いでしょう。
それは、掛布団がフローリングや畳に当たることで、しっかり折れ曲がらずフローリングに広がってしまうからです。ベッドの場合、床から40cm程度上がっているため、掛布団が垂れ下がり、隙間がなくなります。
通常、マットレスのサイズ(長さ)の計算方法は、身長×1.05+15cmです。身長170cmの人の場合、170×1.05+15=193.5cmとなります。
身長測定のときには、かかとから頭のてっぺんを計測しますが、眠るとつま先が少し伸びます。足の大きさは身長と比例する方が多いため、身長に1.05を乗じるのです。
そこに枕の分を10cm、足先からの余裕を5cm、合計15cmプラスの計算となります
ちなみに、世の中に販売されているベッドマットレスの長さのサイズはほとんどが195cmとなっていますが、身長173cm以上の方の場合は、195cmのベッドでは横向き寝にしないと足が出てしまう計算になります。
世界一寿命が長い民族は日本人です。医療の充実や和食が長寿の秘訣と言われておりますが、ふとんマイスターは「仰向き寝文化も健康長寿の秘訣では?」と言っていました。
せっかく同じ時間眠るのであれば、時間の有効活用の点から考えると、マットレスでもできれば敷布団と同様に考えたほうが良いでしょう。つまり長さのサイズは敷布団と同じ計算で、仰向けでゆったりと眠れる身長+35cmの大きさが快眠サイズとなります。
1-3.日本生まれか西洋生まれか
前述の通り、敷布団は日本の着物文化による反物の大きさが横のサイズに関係しています。日本では、メートル法が浸透するまで、尺の文化でした。実は尺には二種類あることをご存知でしょうか?
大工さんが使う尺は一尺30.3cm。着物用の「鯨尺(くじらじゃく)」という単位は37.5cm程度。
ふとんマイスターはじめふとん職人は「2尺で75cm」という単位の使い方をします。37.5cm「程度」というのは、織物産地の織り方によってほんの少し幅が違うから。青梅の綿織物、甲斐の緞子織り、京都西陣織など、さまざまな地方で特色ある織り方があるのですね。
ふとんのつくり方は、縫いあがった生地を裏返し、その上に綿を組みながら積み重ね、ひっくり返します。そうして入れ口を手縫いし、綿が動かないように”とじ”という工程で糸で止めます。人体の体重配分を考慮し、腰が当たるところを多めに綿を配置し、寝心地が良く、腰に良い形状に仕立て上げます。
マットレスは、古代の遺跡からも発見されていますが、もともとは4本の柱を立て、床からマットレスの底に使う板を少し上げ、そこにクッション性のあるものを積み重ねていきます。このクッション性のあるものは、例えば”わら、ヤシの木、ウール”など。これらを積み重ねぐるっと布で包み込み、ベッドメイキングをしていたようです。
1-4.敷布団とマットレスの素材の違い
次に、敷布団とマットレスの素材の違いをみていきましょう。
1-4-1.敷布団の素材
オーソドックスな敷布団の中綿といえば、天然素材の木綿です。最近は中綿も多様化し、羊毛なども使われていますね。ポリエステルなどの合成綿を使った商品はコストパフォーマンスの良さで人気があります。
敷布団の場合は中綿の素材によって、クッション性や保温性、吸湿性や重さが変わってきます。
1-4-2.マットレスの素材
マットレスの素材は、ウレタンやラテックスなどのクッション性の良い新素材が主流です。しかし近年では高反発ファイバーを固めた商品も登場していて、表面の形状はさまざまです。
なかでもウレタンが人気で、体が柔らかく沈む「低反発マットレス」と、反発力があって体が沈みにくい「高反発マットレス」の2種類があります。
2.敷布団とマットレスの正しい使い方と違い
近年、住宅事情がかわり、畳の部屋がない家にお住まいの方も増えました。と同時に、敷布団やマットレスの使い方もさまざまになってきています。 環境の違いによる、敷布団とマットレス の使い方の一例をご紹介します。
2-1.フローリングの部屋で快適に眠るために
近年主流のフローリングの部屋では、一体どのような寝具を選んだら良いのでしょうか。
2-1-1.敷布団で眠りたい場合
木綿や羊毛、化学繊維の敷布団を一枚でフローリングの上に使用する場合、寒い地域の場合は冷えが心配です。その場合には、敷布団の下に敷くマットレスを使用することが考えられます。 またフローリングは畳よりも蒸れやすくなるため、除湿マットなどが必要になります。
2-1-2.フローリングの上にマットレス一枚だけ敷いて眠りたい場合
マットレスと一口に言っても、主に「ベッドマットレス」「敷布団の下に敷くマットレス」「健康マットレス」の3種類があります。
フローリング上で一枚で眠りたい人の90%以上が、健康マットレスの事を指して「マットレス」と呼んでいるようです。この健康マットレスは、ほとんどの場合”ウレタン”を使用しています。ウレタンには大きく分けて2種類「低反発系」と「高反発系」があります。
低反発系は、衝撃を吸収するようにとても柔らかくできています。触った感触は柔らかく、身体を包み込んでくれそうです。しかし、腰の悪い方には向きません。柔らか過ぎてしまうため、起きてから腰に違和感を訴える人が多いです。また、薄くても重く、ムレやすいのが特徴で、夏は柔らかく、冬は硬くなります。
これとは反対の、高反発系は衝撃を跳ね返します。そのため、触れた感覚は硬いのですが、朝、腰の様子が気になる方には高反発系が良いでしょう。また高反発系の方が軽くてムレにくく、一年中ほぼ変わらない硬さを保ってくれます。
これらマットレスは、”ウレタン”を使用したものが多く販売されています。しかしウレタンは素材的に蒸れやすく、さらにフローリングからの冷えが気になる方も。そういう場合はウレタン素材を避けると良いでしょう。
2-1-3.フローリングで直に敷布団やマットレスを使う際の注意点
フローリングに直接敷布団やマットレスを使用する場合、ダニやカビが気になります。
人は一晩にコップ1杯の汗をかくと言われています。その汗の2分の2程度が床の方へ流れてしまいます。朝起きたときに、床が湿っているのを感じたことがあるという人もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
さらに敷きっぱなしにした場合、湿気の逃げ場がないため敷布団やマットレスがカビる原因になります。また、その湿気によってダニの居心地が良くなり、集まりやすくなるでしょう。
よって、フローリングに敷布団に直で敷布団やマットレスを敷く場合は、こまめにお手入れが必要です。決して敷きっぱなしにせず、定期的に干せるようにコンパクトに折りたためるものが良いでしょう。
最近では、部屋干しでOKなマットレスや、軽くて折りたたみができ、持ち運びが楽な敷布団が販売されています。また、櫻道ふとん店さんでは、軽くて折りたため、部屋干しだけで清潔を保てるマットレスを取り扱っているそうです。気になる方は相談してみてくださいね。
2-2.ベッドのマットレスの上に敷布団を敷く場合〜マットレスの使い方〜
ベッドのマットレスの上に敷布団を敷きたい場合は、どのような使い方が快適に眠れるのでしょうか。
2-2-1.ベッドの上に敷布団マットレスを敷くメリット
みなさんは、ベッドマットレスの上に何かを敷いて寝ていますか?一般的には「ベッドパット」と呼ばれる薄い汗取り用のものだけを使用している方がほとんどではないでしょうか。
ベッドマットレスの中身は、高級品になればなるほど、スプリングの上に高反発ウレタン、低反発ウレタン、化繊の綿などが幾重にも重なり心地良さをつくりあげています。もし今使用しているものが50万、60万もするような高級ベッドマットレスであれば、そのままで良いかもしれません。
しかしそうでなければ、ベッドマットレスの上にマットレストッパーとして敷布団マットレスを重ねることをオススメします。コスパよく、より健康的で快適な寝心地を手に入れることができるでしょう。
2-2-2.腰のためや冷え対策としてマットレスの上に敷く場合
腰が痛い人や冷えが気になる人の場合、自然の遠赤外線が出ている敷布団マットレスを重ねると良いでしょう。ウォーターベッドのように身体を包んで温めてくれるため、体調だけでなく睡眠の質も向上します。
2-2-3.ヘタってきたベッドマットレスをカバーするために敷く場合
「経年劣化によりマットレスがヘタってきて、朝起きると腰が痛くなることが増えた」なんて場合も、腰痛対策をうたう敷布団マットレスを重ねることをおすすめします。
その際注意してほしいのが、ベッドマットレスの真ん中部分の凹みの有無です。明らかに真ん中が凹んでいるヘタったベッドマットレスの場合、その上に1cm程度のコンパネ(ベニヤ板)を敷き、更にその上に腰痛対策敷布団マットレスを使用するとより効果的。
コンパネを敷くことで、ベッドマットレスのスプリングが平均的に使用できるようになるのです。マットレスを廃棄することなく、より長い間使えるテクニックと言えるでしょう。これにより、寝ているときの姿勢を正しい方向に導いてくれるので、コスパの良さだけでなく腰への負担が減るのもうれしいですよね。
2-3.敷布団とマットレスを併用したい場合
マットレスの薄さを補うために、敷布団と併用したいと考える人は多いでしょう。
ですが、敷布団もマットレスも基本的に単体で使用することを目的に作られた寝具です。併用することでマットレスの機能性が損なわれることも多いため、慎重に判断をしてください。
ただしマットレスの寝心地が体に合わない場合は、敷布団との併用で改善ができるかもしれません。大事なのは、組み合わせ方です。
たとえばマットレスが硬すぎて寝苦しい場合は、上に敷布団を敷くことで寝心地の改善が可能。敷布団が薄くて床付き感が気になる場合も、マットレスを敷布団の下に敷くことで厚みがでて、寝心地が良くなるでしょう。
低反発・高反発素材で体重分散に配慮された、高機能(健康)マットレスの床付き感が気になる場合は、敷布団をマットレスの下に敷いて使うことをおすすめします。敷布団を上にすると、せっかくのマットレスの機能性が失われてしまうため、注意してください。
3.メリット・デメリットから見るマットレスと敷布団の違いを比較
新しく寝具を買い揃えようとすると、多くの人が直面するのが「マットレスにするか、それとも敷布団にするか」という悩みではないでしょうか。寝具売り場には、マットレスも敷布団も多くの種類が並んでいます。それはつまり、どちらも同様にニーズが高いということでしょう。
双方ともに強みがあり、けっして一方だけが優れているわけではありません。どちらを選ぶべきかは、使う人の環境や好み次第だと言えます。
3-1.適しているのはマットレス・敷布団?メリット・デメリットの違いを知る
では、マットレスを選ぶべきなのはどういう人で、敷布団を選ぶべきなのはどういった人なのでしょうか?それぞれの寝具のメリットとデメリットを見ていきましょう。
3-1-1.マットレスのメリット
マットレスの主なメリットは、以下の3点が挙げられます。
○弾力性に富んでいる
○内部にゴミが入りにくい構造なので清潔
○一般的に通気性が高い
多くの人にとってマットレスの最大の魅力は、やはり「弾力性」でしょう。日本人は10人中6人が腰にトラブルが起きたことがあると言われています。弾力性で体の負担を軽減できるという点は、大きなプラスポイントですね。
さらに通気性が高く虫が湧きにくいので、扱いが簡単というのも強みでしょう。つまり、首・肩・腰に疲れが溜まりやすい人や、忙しくメンテナンスができない人に適した寝具だと言えます。
弾力性が高いマットレスと相性が良いふとんは「羊毛」素材のふとんです。マットレスのクッション性と吸湿性の高い羊毛ふとんを併せて使用することで、毎日サラサラとした寝心地がキープできることでしょう。
3-1-2.マットレスのデメリット
反対に、マットレスのデメリットとしては、次の3点を挙げることができます。
△折りたためない
△保温性が低い
△丸洗いができない
マットレスは、高い弾力性を保つための構造と引き換えに、折りたたむことができないタイプが多くあります。どうしても場所をとってしまうため、部屋を広く使いたい人には不向きです。
そして、通気性が高いということは保温性も低いということ。秋冬は肌寒く感じがちです。丸洗いができないものも多いため、特にお年寄りや小さなお子さんがいるなどマットレスが汚れる可能性が高い家庭は、しっかり確認してからお求めいただくことをおすすめします。
3-1-3.敷布団のメリット
一方、敷布団のメリットとしては次のような点が挙げられます。
○折りたためる
○丸洗いや天日干しが可能
○質のよいものであれば寿命も長い
日本の住宅収納は、もともと布団に適したサイズで作られています。そのため、折りたたむことができれば非常にコンパクトに収納することができるでしょう。家族が多ければ多いほど、よりスペースの有効利用にもつながります。
また、持ち運びが楽な敷布団も増えてきているため、来客用として使うのにも適しています。このようにライフワーク別、または状況によって適した敷布団は豊富にあります。
3-1-4.敷布団のデメリット
デメリットは、次のとおりです。
○日頃のケアを怠ると劣化しやすい
○通気性が悪い
○薄い
ただし敷布団のメリットを存分に味わうためには、敷きっぱなしだけは厳禁です。カビやダニが発生してしまう原因にもなります。特に木綿の敷布団は、素材上どうしても湿気を吸いやすいため、天日干しが必要になります。木綿のような天然繊維の敷布団は高機能で寝心地も良いのですが、毎日の上げ下ろしは必要となってきます。
梅雨の時期や、なかなか毎日のメンテナンスが難しいという方は、布団乾燥機が一台あると色々使えて便利ですよ!4.お手入れ方法で選ぶなら敷布団?マットレス?違いを知ってから選びましょう
毎日使う寝具ですから、お手入れ方法は大切ですよね。寝心地や機能性だけでなく、メンテナンスのしやすさも寝具選びの重要な判断基準のひとつ。
寝具は毎日使う衛生用品ですから、お手入れがしやすく、いつも気持ちよく使えるものを選んでください。 こちらでは、敷布団とマットレスのお手入れ方法の違いを、比較しながらご紹介いたします。
4-1.敷布団のお手入れ方法【機能性マットレスとの違い】
木綿の敷布団のように、体の下に敷いて使う寝具は寝汗による湿気が溜まりやすい傾向があります。定期的に干して、乾燥させる必要があります。お天気の良い日を選んで、木綿の敷布団はこまめに天日干しをしましょう。干す時間帯は湿度の低い午前10時から、午後3時頃までがベスト。
とは言え、長時間の天日干しは、敷布団の生地を劣化させるリスクがあります。トータルで2〜3時間程度を目安に、途中で敷布団をひっくり返して、両面をしっかり干しましょう。この作業は、1ヶ月に一回程度で大丈夫です。
側生地や中綿によっては、天日干しができない敷布団もあります。必ず取扱説明書を確認してから干してください。
説明書に天日干しが可能とあっても不安な場合は、専用のカバーやシーツで覆ってから天日干しをすると、紫外線の影響を最小限に抑えることができます。
なお、羊毛敷布団は、湿気を自然に放散してくれるため基本的には部屋干しでも大丈夫です。外に干す場合は、カバーで覆って干しましょう。 化繊の敷布団の場合、大型のコインランドリーで洗うことができるところが嬉しいポイント。清潔を保つことができます。
4-1-1.敷布団のお手入れの際の注意点
敷布団を干すとき、ホコリを払うためについついやりがちなのが、ふとんを強く叩く行為です。これは絶対にNG。ふとんが傷むだけでなく、ダニの死骸を粉砕してしまい敷布団の奥に入り込んでしまうことに。ハウスダストなどのアレルギーを引き起こす原因になりかねません。敷布団のホコリが気になる場合は、室内に取り込んでから、表面に掃除機をかけて取り除きましょう。
また、嫌な臭いや肌触りの悪化も寝苦しさの原因になるため、汚れを放置することも厳禁です。ジュースなどを敷布団にこぼしたときは、すぐにつまみ洗いをして汚れを取り除き、その後しっかりと乾燥させましょう。
ご家庭の洗濯機で洗えるウォッシャブルタイプの敷布団ならお手入れしやすく、汗っかきな人でもとても衛生的に使えます。大きい敷布団や洗濯機に入らない場合は、大型コインランドリーや専門店のふとんクリーニングなども活用して、敷布団はいつも清潔に使いましょう。
4-2.機能性マットレスのお手入れ方法【敷布団との違い】
マットレスは敷布団とは違い、サラッと天日干しするだけで良いものが多いです。ただそうは言っても、寝汗や皮脂などで汚れやすいのは同じ。シーツやカバーでマットレスを覆い、こちらをこまめにクリーニングすると、清潔に使用できます。
また、マットレスは敷きっぱなしではいけません。こまめに壁に立て掛けるなどして風を通し、寝汗による湿気を取り除くと良いでしょう。マットレスの下にすのこや除湿シートを敷くのも、湿気の蓄積を防ぐのに効果的です。
4-1-2.マットレスのお手入れの際の注意点
基本的にマットレスは敷布団のような「丸ごと洗う」ケアはできません。そのため、汚れないようにしっかり対策をして使うことが大切です。汚れは嫌な臭いの原因につながります。前述のように、必ずカバーやシーツ、敷パッドなどで覆って使いましょう。
最近では、汗取り敷パットなども販売されています。シーツなどと併用するととても効果的です。
また、マットレスは定期的に裏表や上下を入れかえて、ローテーションして使うことをおすすめします。長期間使っていると、最も体重がかかる腰回りの部分がつぶれてしまいがちです。ローテーションで寝る場所を入れ替えることで、寝心地が悪くなるのを防いでください。
5.タイプ別おすすめ!マットレスと敷布団、あなたに合うのはどっち?
それぞれの違いが分かったところで、敷布団やマットレスがどんな人におすすめなのかを解説していきましょう。
機能性にこだわって寝具を選ぶことも大切ですが、メンテナンス性など、日々の使い勝手の良さもとても重要です。毎日使うものだからこそ、総合的に自分に合っているかどうかも見極めましょう。
5-1.マットレスよりも「敷布団」がおすすめな人
上げ下げしやすく、三つ折りなどにして簡単に片付けられる敷布団は、お部屋を広く使いたい人におすすめです。ベッドを使わずに床に直敷きできるため、ワンルームのアパートにも最適。
簡単に上げ下げできるのでお部屋のお掃除もしやすくなり、ホコリの蓄積やふとんにこもった湿気でカビや雑菌が繁殖するリスクが少なくなるのも大きなポイント。天日干しや丸洗いをすることで衛生的なケアもできます。汗っかきな小さなお子さんやアレルギーが気になる人でも安心でしょう。
また敷布団は、身近な店舗で気軽に購入でき、お値段もお手頃です。コストを抑えたい人や、新生活でとりあえず寝具を必要としているなど、急いでいる人にもぴったりです。
5-2.敷布団よりも「マットレス」がおすすめな人
マットレスは、素材の多様化が進んでいます。通気性が良く洗えるマットレスやとことん軽いマットレス、折りたためるマットレス、ダニ、カビに対応したマットレス、天然の遠赤が出るマットレスなどが挙げられます。
敷布団より少しお値段が張るものの、硬さや柔らかさなどの反発力が商品ごとに違い、機能的なのも魅力ですね。腰痛の改善や熟睡のしやすさなど、睡眠の悩みを抱えている人でも自分に合ったものを選びやすいといえます。
ウレタンなどの新素材はダニの温床になりにくいので安心です。敷きっぱなしだけ避ければ、天日干しの必要がなく、軽く風通しをする程度で良いのがポイント。お手入れの手間をかけたくない人にもおすすめです。
6.敷布団とマットレスの違いを知って、自分のスタイルに合う寝具を見つけましょう
敷布団と機能性マットレスの細かな違いを、櫻道ふとん店のふとんマイスター監修のもと解説いたしました。どちらにもメリットデメリットはあり、それはその人それぞれの生活スタイルや環境によっても異なることが分かりましたね。自分にぴったり合った寝具を使い、正しいお手入れで清潔に保ちながら、快適な睡眠を手に入れましょう。















